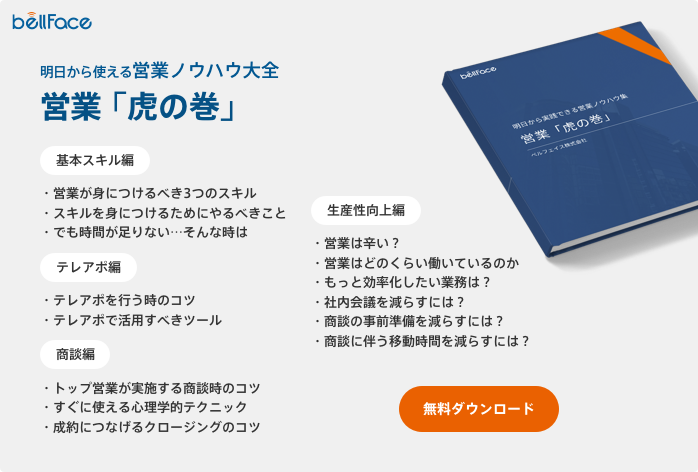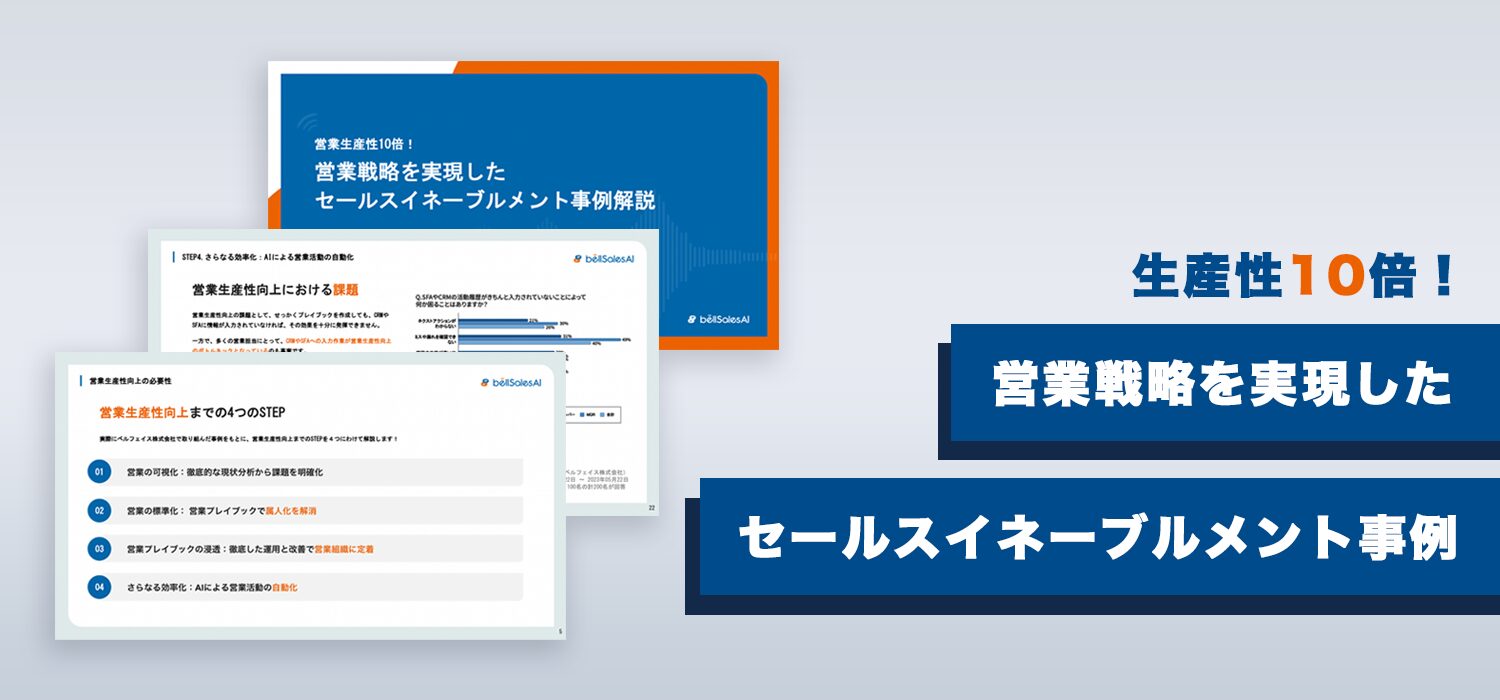営業活動の成績をアップさせるために欠かせないのが、コミュニケーション能力です。営業は一人だけで完結するものではなく、必ず相手が存在します。その相手に自分や商品を上手く知ってもらうためには、自身のコミュニケーション能力を磨いていかなくてはなりません。
しかし、具体的に何をすればコミュニケーション能力は向上するのでしょうか。またどうやってコミュニケーションスキルを活用していけばいいのでしょう。
今回は、そんな営業で欠かせないコミュニケーションスキルについて解説します。営業でのコミュニケーションを活性化させる便利なツールもご紹介するので、併せてチェックしてみましょう。
営業で使いたい5つのコミュニケーションスキル

まずは営業活動で活用すべき、刺さる5つのコミュニケーションスキルをご紹介します。コミュニケーションスキルは普段意識していないだけで、多くの方が無意識に使っています。
お客様との商談が成功した際などは、自然とコミュニケーションスキルを使いこなせていた場合が多いです。以下に紹介するスキルはどれも代表的なものなので、相手とコミュニケーションを取る際に、改めて意識してみるといいでしょう。
徹底して相手に共感する
友達や恋人などに話をしていて嬉しかった瞬間は、どんな時でしょうか。話が盛り上がった時、相手が笑った時など色々あると思いますが、そこには共通しているポイントがあります。
それは、「相手の共感が得られている」という点です。話してみたら共通の趣味があって、お気に入りのバンドも一緒だった、愚痴を聞いていたら全く同じ経験があり思わず笑ってしまったなど、コミュニケーションにおいて相手に共感するのは基本であり、最も大切なポイントです。
営業で相手との会話がいつも盛り上がりに欠けてしまうと悩む方は、まず相手の会話に徹底して共感できるように心がけてみましょう。
メリット・デメリットは明確に話す
臆さずに、商品のメリットとデメリットの両面を話すようにしましょう。最初はデメリットを話すのに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、お客様の立場からするとデメリットを話してもらえた方が安心できます。人生経験が長い人ほど、物事には良い面・悪い面があるのを理解しているからです。
例えばサービスが充実している契約でも、料金が高額になるのであれば、料金体系については明言しましょう。高額の料金を曖昧にして契約すると、後々にトラブルに発生するケースもあります。
お客様にはメリット・デメリットの両面を正しく理解していただき、末長く商品を使っていただきましょう。
相手の話を傾聴する
傾聴(けいちょう)とは、もともと心理カウンセリングの場で使われてきたコミュニケーション技術です。耳だけでなく、目も心も傾けて相手の話を聴く姿勢のことを指します。
会話が途切れて無言になってしまうのではないか、という恐怖は誰しもが抱くものです。自分がたくさん話して場を盛り上げて、商談に持ち込みたいと考える気持ちもあるでしょう。
しかし、お客様の立場に立とうとする姿勢も忘れてはなりません。お客様の中には悩みや不安、問題を抱えていて、実は相談したいと思っている方も多くいらっしゃいます。そんなお客様の要望を見抜いてあげるのも、大切な営業スキルの一つです。
自分ばかり話してしまっていると感じたら、一旦落ち着いてお客様にも話を投げかけましょう。そして、なるべくその話を深堀りし、広げるように心がけましょう。
他社事例紹介で利用イメージを植える
いくら営業トークで上手く商品の魅力を伝えられたと思っても、お客様の気持ちをもう一歩動かしきれない場合もあると思います。そんな時は、具体的な商品の活用事例を伝えてみましょう。
お客様は、商品の素晴らしさを納得するための根拠を求めています。そこで実際の他のお客様の導入事例を提示できれば、説得力は抜群です。事例の話を聞けば、お客様も実際のイメージも膨らませやすいですし、実際に使ってみたらどうだろうと想像も膨らみます。
実例では何がどう変化したのか、わかりやすく伝えましょう。実際の利用者の意見も用いながら説明すると、より効果的です。
営業トークに囚われない
営業活動にも少し慣れてきた、そんな時に気をつけたいのが、営業トークに囚われないことです。何度か成功体験をすると、打率の高い自身の営業トークというものも見えてきます。
これは確実にスキルアップしている証拠なのですが、その自身の営業トークに固執しないようにしましょう。
営業トークに囚われ過ぎると、周りが見えなくなり、お客様の話も耳に入らなくなってしまいます。そうなると、真にお客様のニーズにあった商品の提案はできなくなりますし、さらなる営業スキルの向上も停滞してしまいます。
営業トークに夢中になっていると感じたら、俯瞰して自分をみてみるようにしましょう。
【もっとスキルを広げたい方はこちら】デキるTOP営業の必須スキルを徹底解説!
こんなコミュニケーションは危険!

ここでは営業においてNGとされるコミュニケーションとその対策を紹介します。
一方的に話す
営業側が途切れることなく一方的に話してしまうと、お客様は聞いていて疲れてしまいますし、話の内容が伝わらないばかりか、信頼を得ることすら難しくなってしまいます。
一方的に話さないための対策を3つ紹介します。
相手に興味関心を強く持つ
相手の気持ちや情報を知りたいという関心を持つことは、信頼関係を構築するうえで重要な要素です。人は自分のことを深く理解してくれる人に対して信頼や好感を抱きます。そのため、お客様との信頼関係を築くには、まずは相手に関心を持って接することが重要です。
お客様と会話する際は、お客様の要望や性格、自分との共通点などを聞き出したり、引き出したりすることに意識を向けましょう。
お客様のことを理解しようと関心を向けることで相手への理解が深まりますし、お客様側も、自分の要望や悩みを理解してくれる営業側に対して強い信頼を寄せるようになるでしょう。
相手の心理を読み取る
コミュニケーション能力が高い人は、人の心の奥深くにある「本当の気持ち」や「真意」を捉えることに長けています。お客様はただ報告したいのではなく、何か伝えたいことや分かってもらいたいことがあって話をしています。
したがって、お客様が話を切り出してきたときに機械的に反応するだけでは相手の話に興味がないと思われてしまい、お客様は「話しづらい営業だ」と感じてしまうでしょう。
そのため、言葉通りにそのまま理解するのではなく、時には言葉の裏に隠れている気持ちや真意を読み取る努力も必要です。
また、相手の言葉や話の内容だけでなく、表情や口調などの「非言語」からも情報を得て、相手の立場になってコミュニケーションを取ることで、大きな信頼を得ることができます。
ペースを合わせる
お客様の話すペースに合わせることで一体感を作り出し、短時間で信頼を得たり、打ち解けあったりすることができます。
具体的には、お客様の話すスピードやリズム、声の大きさ・抑揚、使う言葉、表情・ジェスチャーなども意識して合わせると一体感を作りやすくなります。
上手く一体感を作ることができればお客様は営業パーソンに対して安心感・親近感を持ち、購買に向けてポジティブな行動や反応を示すようになります。
また、どんな人でも日によって体調や気分が異なります。したがって、日々変化するお客様の心理や体調などの状態を読み取って話し方を変えればより一体感を作る出すことができるでしょう。
他社製品・サービスの悪い点を言う
他社製品・サービスの悪い点を言うこともやってはいけないことです。お客様に「他社製品の悪口を言ってまで商品を売りたいのか」などと思われて、自社の品位を落としてしまいます。人は悪口を言われると意固地になり、褒められると謙遜する傾向があります。
したがって営業パーソンがやるべきことは、もしお客様が他社製品を利用しているならば、その他社製品を褒めて謙遜を引き出し、相手が感じている欠点の部分を聞き出すことです。
もちろん率直に「◯社の製品、いかがですか?」と尋ねるのもよいでしょう。決して自分からは他社製品を悪く言うことなく、お客様から他社製品への不満点を引き出しましょう。
自信のない話し方
お客様は「自信があり、信頼できる人」から商品を購入したいと考えているので、営業パーソンが自信のない話し方をすると、お客様も不安になり商品を購入してもらうことは難しくなります。
自信のある営業パーソンは快活で適度にゆったりと話し、何を言っても受け止めてくれそうな安心感があります。
自信が持てない方や自信を高めたい方は、トップセールスマンのふりをしたり、理想の自分になりきったりすることで、自信があるように話すテクニックを磨きましょう。
相手に合わせない連絡手段
営業時のマナーとして、昼休み中や退勤間際の時間に営業の電話を掛けることや、深夜帯にメールを送ることは避けるべきですが、相手の嗜好にあった連絡手段をとることも重要です。
メールを好む顧客、電話を好む顧客、実際に会って話すことを好む顧客がいますが、顧客の嗜好に合わない連絡手段でアプローチをし続けても、信頼関係を築くことは難しくなるでしょう。信頼関係を築くために、顧客ひとりひとりの嗜好を記録しておき、実践しましょう。
ただし、謝罪や緊急の案件が発生した場合は、メールを好む顧客であってもまず電話をし、実際に会って対応したほうが良いでしょう。また、進捗条件の確認や近況伺いの挨拶であれば、顧客が時間を選べるメールを使った方が無難です。
営業のファーストコンタクトはメールor電話?正しいのはどっち?
コミュニケーションスキルを磨くには?

続いて、コミュニケーションスキルを実際に磨いていくには、どんな方法があるのでしょうか。コミュニケーションスキルをもっと上達させたいと感じても、具体的に何をすれば良いか迷ってしまいますよね。そんな方に向けて、以下の具体的な方法をご紹介します。
とにかく商談へ行く
リストアップなど、営業活動の準備ばかりに時間を取られていないでしょうか。
準備も確かに大切ですが、実際に行動してお客様と話をしないと受注には結びつきません。コミュニケーションスキルをアップさせるためにも、迷ったらとにかく商談をこなしましょう。
上手くいく商談は少数かもしれませんが、全ての商談をダメだったと切り捨てるのは少し早いです。具体的にどうダメだったのか、忘れずに分析も行いましょう。
なかには手応えはあったけれど、最後のクロージングで失敗したケースもあったはずです。良かった点と悪かった点をそれぞれ明確にして、次の商談へと向かいましょう。
【営業のクロージングとは】成約率を上げる15のコツとプロセスを解説
社内にて練習する
自分の身近な人に協力を仰ぐのも、有効な手段です。普段忙しいと、自分の仕事だけで精一杯になり、周りが見えなくなりがちですが、同じ部署の仲間はライバルであると同時に大切な仲間です。
営業活動で悩んでいるならば、恥ずかしがらずに周りに助けを求めてみましょう。きっと誰もが快く助けてくれるはずです。アドバイスや心構えを伝授してもらえるかもしれません。
機会があれば一緒に営業のロールプレイをしてもらえないか頼んでみましょう。実践のような練習ができ、たとえミスをしても気に病む必要はありません。何度もリトライできますし、改善点も明確になるはずです。社内で練習してレベルアップしましょう。
セミナーや展示会などで交流を深める
セミナーや展示会を利用するのも効果的です。目的にあったセミナーに参加すれば、必要な知識を学習できます。講師の方に、気になるポイントは質問できるので、コミュニケーションスキルの向上も期待できます。
さらに、受講者同士の横の繋がりも広げるチャンスです。ここで得た仲間は、困った際の大きな支えとなってくれるはずです。同じセミナーに参加した同士なので、共通項も多いでしょう。
ちょっとしたことでも相談してみると、問題が前進するきっかけになります。同様に、展示会でも交流を深める機会は多いので、有効に活用してみましょう。
「ヒアリング」についても意識する
コミュニケーションは話すだけでなく話を聞いたり、聞き出したりするヒアリングも重要です。営業側が要望や課題などをどれだけ深くヒアリングできたかによって、受注率が変わってきます。
お客様は営業パーソンのヒアリングを通して、課題解決力があるかどうか、どのくらい有能な人物なのかを推し量っています。お客様へ適切なヒアリングを繰り返すことに成功すれば信頼関係が生まれ、お客様が自己開示を積極的にしてくるでしょう。
ヒアリングに慣れていないうちは、お客様が求めているものやスケジュール感、競合他社の有無など抑えておきたい事項をヒアリングシートとしてまとめておくことをおすすめします。
また、ヒアリング力を磨くためには、優秀な営業パーソンの商談に同行してヒアリングの技術を学んだり、ロープレを行いレビューしてもらったりすると良いでしょう。
伝えたい内容についてしっかり把握する
自信を持って話をするために、商品知識やサービスの内容などをしっかりインプットしておきましょう。ここでは伝えたい内容を把握したうえで、説得力を高めるコミュニケーション方法について紹介します。
PREP法
PREP法は、話の構成の中で相手の心理状態を想定し、先回りして話を持っていく手法です。もともとは文章を書く際に使われる手法ですが、話す際にも応用することができます。
話す内容を「要点(Point)」「理由(Reason)」「具体例(Example)」「結論(Point)」の4つで構成することで、論点や疑問点を簡潔に押さえた説得力のある話し方になります。
以下にPREP法の流れを説明します。
- 冒頭にPoint(提案内容)や結論、答えを伝えます。
- 聞き手には「なぜ?」という疑問・興味が起こります。
- 聞き手の「なぜ?」に答えるReason(理由)を伝えます。
- 聞き手は「なるほど」という関心と「本当に?」という疑問が起きます。
- 「本当に?」の疑問の証拠となるExample(事例や具体例)を伝えます。
- 聞き手は間違いないと確信します。
- 改めてPoint(結論)を強調します。
マジックナンバー3の法則
人が1度に認識できることは3つまでと言われています。そのため、人は根拠やポイントが4つ以上あるとひとつひとつの記憶が薄まり、2つだと少なく感じてしまうようです。
したがって、「マジックナンバー3の法則」に基づいて情報の信頼性を高めるために根拠を3つ挙げることが有効だとされています。
話のポイントや理由、メリットを3つ示すことで相手の記憶に残りやすくなり、インパクトを与えることができます。
数学的根拠の使い方
数字は、表し方を変えるだけで与える印象が異なります。たとえば、減量成功の話の場合は「0.5kgの減量に成功した」よりも「500gの減量に成功した」と言うほうが、聞いている相手にインパクトを与えます。同様に薬の成分量を宣伝する際は、2gを2000mgとして宣伝するほうがよりポジティブな印象を与えます。
また、イメージの湧かない事柄でも、たとえば150gを文庫本1冊として表すなど、数字が表す感覚を別のもので表すことで説得力が上がります。このように数字を使う際は、その表し方も意識してみましょう。
まとめ

今回は営業で活用できる、刺さるコミュニケーションスキルについて詳しく解説してきました。
営業活動は誰しもが苦労するものです。営業でもっとコミュニケーションスキルをアップさせたいと感じている方は、上述した方法を参考にして自分にあったスタイルを探してみてください。
無理なく続けられるのが、営業活動を嫌いにならずに上達させる秘訣です。