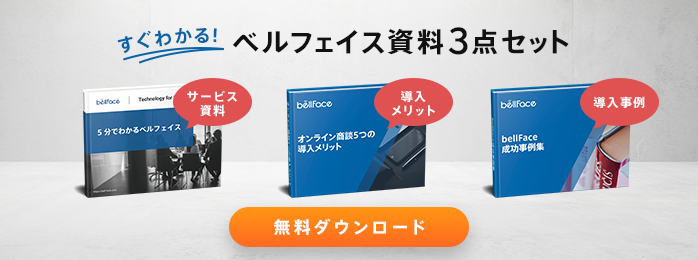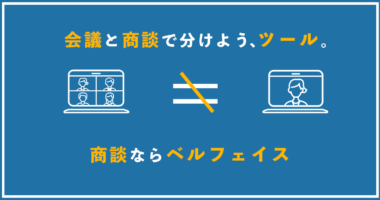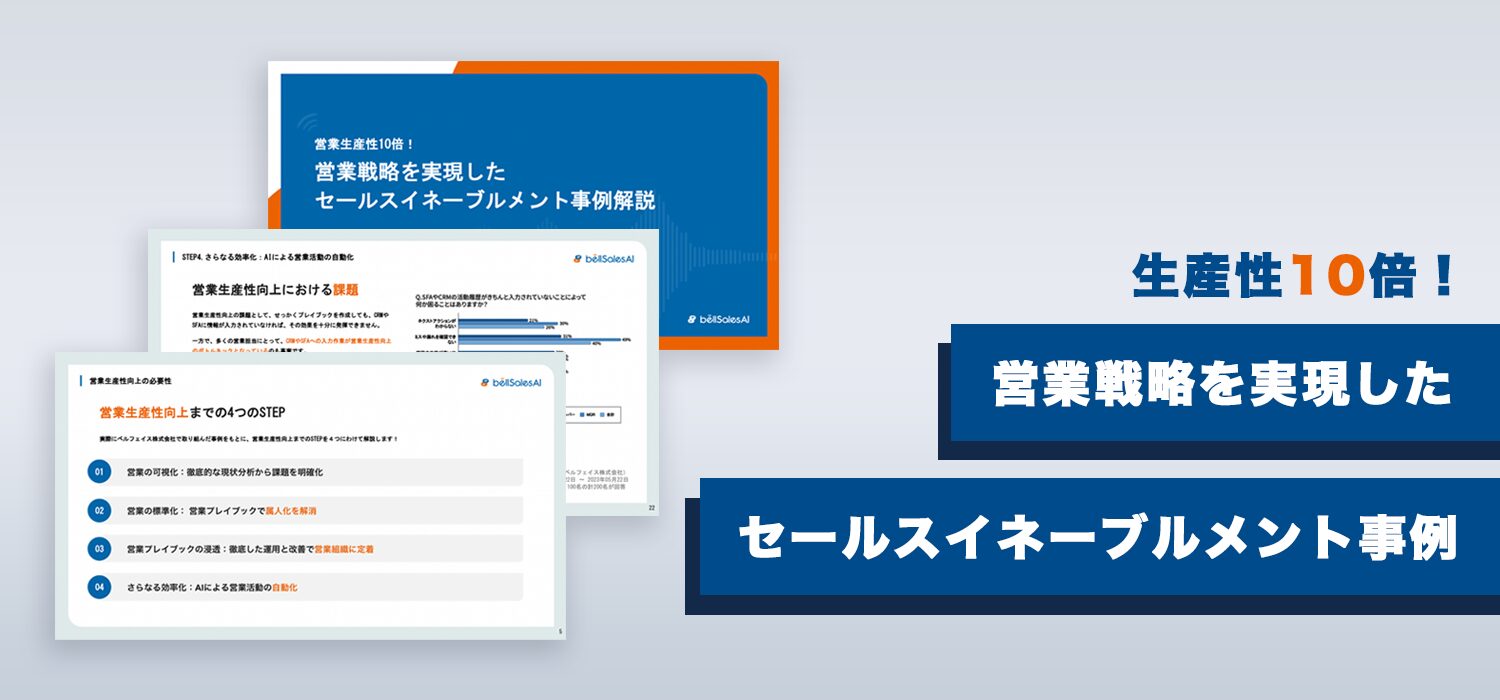未だ新型コロナ終息の兆しが見えないなか、中小企業においても感染拡大防止のために、日々さまざまな対策が行われています。テレワークもその1つですが、中小企業の中には、業務効率や生産性に対する不安から、なかなか導入に踏み切れないと考える企業も多いのではないでしょうか。
あるいは、テレワークは大企業が取り入れるものというイメージが強く、「自社には必要ないのではないか?」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。そこで本記事では、中小企業がテレワークを導入するメリットや、今だからこそ中小企業に導入をおすすめする理由についてご説明します。
中小企業のテレワーク導入は遅れている

デル テクノロジーズが2020年7月に発表した「中小企業のテレワーク導入状況に関する調査結果」によると、全国の中小企業(従業員数1~99人)の経営者および従業員1,072人のうち、「導入している」と答えたのは36%でした。
3月時点の13%から上昇しているものの、依然約6割の中小企業がテレワークの導入に至っていないという結果です。
また、東京商工リサーチが9月に発表した「第8回 新型コロナウイルスに関するアンケート調査」では、「在宅勤務・リモートワークを実施していますか」という項目において、「現在実施している」と回答した中小企業(資本金1億円未満 10,827社)は29.05%(3,145社)でした。これは、大企業(資本金1億円以上 2,153社)の導入割合61.31%(1,320社)に比べて半数以下となります。
さらにこのアンケート結果では、「新型コロナ以降に実施したが、現在は取りやめた」との回答が、大企業で22.53%(485社)、中小企業で22.91%(2,481社)となっており、テレワークを取りやめた企業が、企業規模に関わらず3割近くいるということが明らかになりました。
テレワークの導入が進まないのはなぜ?

先ほどの調査結果でもわかるように、中小企業ではテレワークが進まないばかりか、テレワークを実施したにも関わらず、従来の出勤スタイルに戻ってしまうケースもあります。
このような現状になる背景には、何があるのでしょうか。先ほどの調査やアンケート結果などを参考に、中小企業のテレワーク導入を阻む主な原因を読み解いていきます。
テレワークできる業種ではない、適した業務がない
中小企業庁がまとめた、2020年版「中小企業白書」第1章第5節に掲載されているアンケートによると、中小企業でのテレワーク導入を実施しない理由として、最もよく挙げられていたのが、「業務がリモートワークに適していない」というものでした。
たしかに、工場の作業者や機械オペレーター、建設作業員、福祉や医療関係など、現場で直接人の手で行うような業務を、完全にテレワーク化することは難しいでしょう。しかし、人事や経理、総務といった間接部門であれば、中小企業であってもリモートで対応できる場合があります。
中小企業では、1人の社員が営業と事務、あるいは営業と現場作業など、兼務をしているケースも多いかと思いますので、対応できる業務だけテレワークを取り入れるなど、部分的に導入するという方法もあります。
効率や生産性が落ちるおそれ
業務の進行についての懸念や生産性に対する不安も多く挙げられています。これはテレワークだけの問題ではなく、中小企業における業務効率が主な原因であるケースが少なくありません。
中小企業では、業務の多くが紙ベースで行われているケースも多く、デジタル化に対応していない業務が多いことが、在宅勤務を非効率に感じさせる原因の1つになっています。
また、オフィスであれば簡単なやりとりで済む業務上の会話も、テレワークになると、コミュニケーションそのものが難しいと感じる中小企業の方も多いようです。しかしこれも、チャットツールやWeb会議システムといった、デジタルツールを取り入れることで解決できます。
企業規模が小さく必要性を感じない
業績に対する不安要素以外に、社員数が少ないことや、企業規模が小さいために、テレワークを取り入れるほどではないと感じている中小企業も多いかと思います。
しかし緊急事態宣言中のような、通常の勤務スタイルが難しくなった場合を考えると、むしろ、社員数が少なく規模が小さいからこそ、テレワークは導入するべきといえます。緊急時のリスク軽減はもちろんですが、人材確保やオフィスの維持費といった面でも、テレワークの導入によって中小企業が受けられるメリットは、実はいくつもあるのです。
導入を後押し!さまざまな補助金・助成金が活用できる
政府では、コロナ禍以前からテレワークの普及促進に取り組んでおり、様々な普及促進関連事業が行われています。
また、各地域の自治体でも独自の助成制度が設けられているため、自社の地域でどのような助成制度があるかを確認し、有効に活用してみましょう。ここではその一部をご紹介しますが、どちらも2020年度の申込はすでに終了しています。次年度以降の募集開始に備えて、詳しい情報を確認しておくとよいでしょう。
中小企業・小規模事業者などに向けた、ITツール導入経費の一部を補助してくれる制度です。
通常枠(A、B塁型)と、新型コロナによる特別枠(C類型)とあり、それぞれ通常枠では費用の1/2、特別枠では最大3/4が補助されます。
中小企業事業主に対して、テレワーク実施にかかった費用の一部を助成する制度で、厚生労働省が実施しています。
令和2年度の受付けはすでに終了していますので、来年度に向けていつ受付けが開始されてもいいように、制度についてしっかり把握しておきましょう。
こんなにあった!中小企業がテレワーク導入で得られるメリット

テレワーク導入のメリットとして、作業の効率化や生産性アップが挙げられますが、果たして中小企業においても同様のメリットが得られるのか、不安に思う方もいるでしょう。
ここでは、中小企業にとってのテレワーク導入メリットについて、詳しくご紹介します。
生産性向上・人手不足の解消
生産性向上のためには、業務フローの効率化は欠かせません。デジタルツールを利用することで解決できる課題も多いということは、すでにご説明した通りです。さらに、テレワークの持つ「場所や時間の制約を受けない」という特徴を活かすことで、従業員の作業効率アップだけでなく、離職率の低下も期待できます。
出産や育児、家族の介護といった理由から出社が難しく退職せざるを得ない場合でも、在宅勤務であれば空いた時間に業務を進めるといった働き方ができるため、従業員は離職のリスクや、復職への不安も解消されるでしょう。
慢性的な人手不足に悩まされる中小企業にとっても、人手不足が解消できるため、双方にとってメリットになります。
多様な人材確保につながる
テレワークを取り入れた多様な働き方を促進している企業では、取り入れていない企業よりも、企業イメージがアップする傾向にあります。
コロナ禍以前から推進されている働き方改革をはじめ、副業率の増加、ライフワークバランスへの意識の変化もふまえると、いま企業に求められているのは、場所にとらわれないフレキシブルな職場環境と勤務形態です。
テレワーク導入による企業のイメージアップが、ブランディング強化にもつながり、求職者に対して大きなアピールポイントになります。
場所の制約を受けないため、採用条件から地理的条件が不要になり、遠方や海外からの応募者を採用さえも可能になり、より幅広い人材の中から、自社の企業に合った人材を確保できるようになるでしょう。
オフィスにかかる固定費の削減
常駐の社員を在宅での勤務に切り替えることで、オフィスの固定費を削減できるというメリットもあります。
事務的な業務をデジタル化すれば在宅でも業務が行えるため、その分設備を少なくできたり、Web会議ツールを利用することで広い会議室が不要になり、オフィスそのものを縮小することもできるでしょう。オフィスにかけていた賃料を抑えることにつながります。
オフィスの広さに制限がなくなれば、どこにオフィスを構えるかといった点でも自由度が上がりますし、サテライトオフィスやシェアオフィスを利用するといった選択肢も出てきます。
その他にも、テレワークに伴うデジタル化によってペーパレス化が進めば、紙や印刷にかかるコストを抑えられます。
BCP(事業継続計画)対策
テレワークを普段から取り入れ、オフィスに依存せずに業務を行える環境を整えておくことは、いざという時の備えにもなります。特に災害などでオフィスの機能が停止した場合、規模の小さい企業ほど、復旧にかかる費用や収入面など、事業再開までのリスクが高くなります。
そうなると、中小企業にとっては一時的な休業だけに留まらず、経営の悪化や、事業の継続自体が難しくなってしまうことも考えられるでしょう。
緊急時でも、すぐに在宅勤務やリモートでの対応に切り替えることができれば、事業の立て直しや継続もスムーズにでき、さらに従業員の安全を確保しながら業務を行うことができます。これらの面からも、テレワークはBCP対策として有効です。
中小企業のテレワークは「スモールスタート」がポイント

最初から業務のすべてをテレワークに対応させようと思うと、ノウハウもないまま手探りで行うことになってしまいます。そのような状態では、テレワークの強みである業務効率化や、生産性の向上といったメリットが得にくいため、うまく行かず結局以前の勤務スタイルに戻ってしまうことも考えられます。
そこで、中小企業でテレワークを活用する場合は、まずは営業チームだけに絞るなど、業務の切り替えがしやすい部署から進めていくスモールスタートの方式をとるのがよいでしょう。
限定的にスタートし、オンラインやデジタルツールをどのように自社の業務に取り入れるか、効率的な方法を探りながら、それぞれの業務に合わせたマニュアルやフローを構築していくことが肝心です。
テレワークを行う部署を限定し、担当者がテレワークだけでの実績を積み上げ、そのノウハウを他の社員と共有することで徐々にテレワークの導入を進めていった事例もあります。
▼スモールスタートを実践した詳しい事例はこちら
ベルフェイス活用で営業の仕組み化に成功。たった一人で始めたオンライン商談が組織に根付き、拡がったその理由とは?
まとめ
各調査結果を見ても、大手に比べて中小企業のテレワーク導入率が低い事実は否めません。しかし、中小企業のテレワーク導入を躊躇させている要因は、業務のデジタル化や、スモールスタートで解決できます。
ベルフェイスのようなテレワーク時に便利なオンライン営業ツールには、一般的なWEB会議ツールとは違いオンライン商談に役立つ様々な機能が備わっています。専任コンサルタントによるサポートがある点も大きな違いで、テレワークの導入に不安を抱える中小企業の方でも安心して導入することができるでしょう。
デジタル時代に必要なのは、オンラインと対面を両立できることです。この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を読んだ方におすすめ
・商習慣の激変で営業はどうなる?未来の処方箋
・【働き方改革】営業職のリモートワーク推進の課題考察と3つの役立つツール
・厚生労働省のテレワークモデル就業規則に学ぶ、すぐわかる在宅勤務のルール