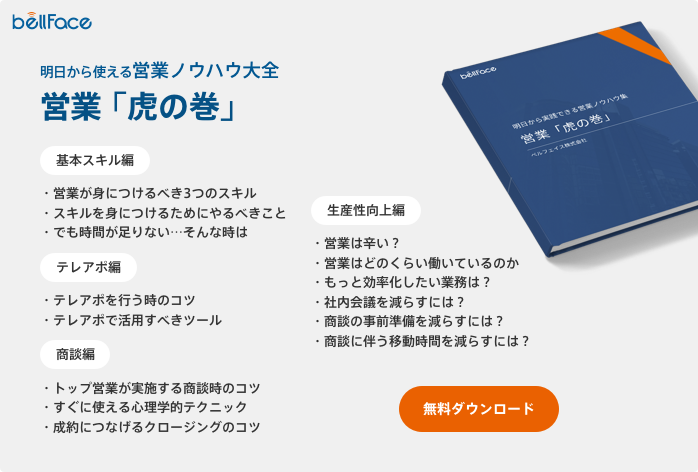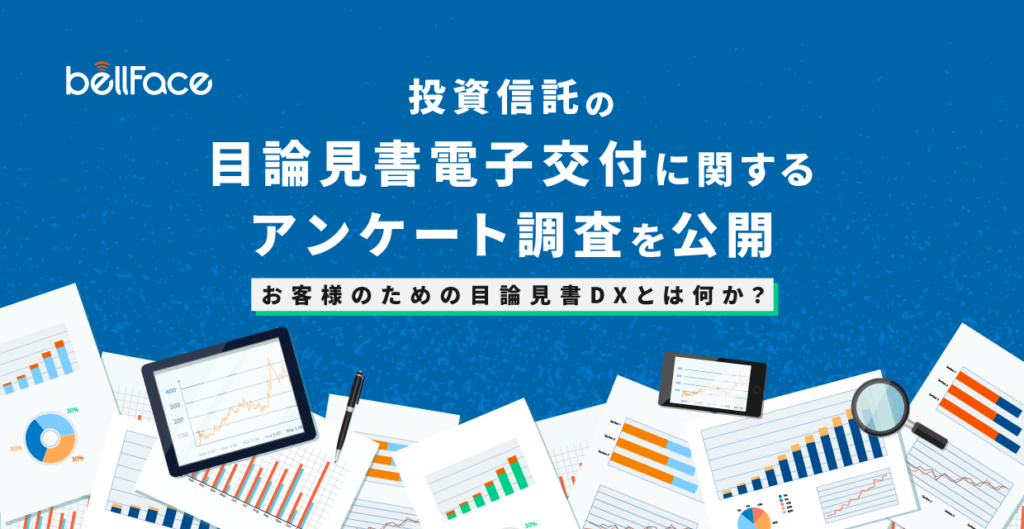この記事では営業活動で重要なベネフィットについて紹介、解説を実施しています。従来のメリット型営業との違いや、ベネフィットを意識した営業方法に関しても詳しく解説していきます。
そもそもベネフィットとは?

営業活動を行う上で、「ベネフィット」という用語は多く耳にする言葉です。会社が提供する商品やサービスを使用したユーザーが獲得できる効果、利益、解決策、価値、将来像といった要素が、営業シーンにおけるベネフィットとして扱われます。
また、ビジネス以外の場においては、人や社会に良い影響を及ぼす恩恵、利便性の提供、支援活動、慈善事業といった意味で用いられることもあります。
ベネフィットの例としては、クーラーを購入する顧客は部屋を涼しくするという効果や暑さへの解決策を得たいからであり、宝石を購入する顧客は高級品を持つというステータス、価値、他人に対するアドバンテージという効用を得たいから、等が考えられます。
商品やサービス自体に関する説明ではなく、ベネフィットは「結果に焦点を当てて説明したもの」です。宣伝広告のキャッチコピーとしてベネフィットを記載することで、商品やサービスが持つ主な魅力を効果的に宣伝することが可能です。
ベネフィットとメリットの違い
導入による効果を説明するという意味では、「ベネフィット」と「メリット」は似たような意味を持つ言葉です。実際に混同されることも多いですが、それぞれの意味を理解して正確に使い分けられると、営業効率を確実に向上させることができます。
まず、「メリット」とは商品が持つ特徴や長所を説明した言葉です。対して、「ベネフィット」はユーザーがメリットを得ることでどういった変化、結果を得るかを説明した言葉です。
導入したい商品やサービスが決まっている顧客であれば、メリットを伝えることで自社製品の魅力を効果的にアピールすることが可能です。
例えば高機能なスマートフォンを探している顧客の場合、バッテリー容量やストレージの大きさなどを説明するだけでも購入してくれる可能性は充分あります。
しかし、購買意欲が低い相手へ商品の機能や長所を説明しても良い反応は見込みづらいでしょう。先程のようにスマートフォンで考えると、長距離の移動でもバッテリーが切れない、写真や動画などをたくさん保存できる、等の説明をしたほうが興味を持たれやすいと言えます。
ベネフィットから伝えるようにするだけで、顧客の関心を大きく引き寄せる効果が見込めます。
営業時はベネフィットトークが大事!

新規顧客の課題やニーズを的確に引き出すには、ベネフィットの把握や提案を意識して営業トークを構築、実践することが有効な手段です。
これから述べる3つのポイントを営業スタイルに反映できれば、今までベネフィットを意識してこなかった営業職の方も自然なベネフィット型営業の流れを把握することが可能です。
リスクや懸念点も伝える
ベネフィットを意識した営業では、顧客のニーズを実現できるという言葉だけではなく、必要なコストや前提条件に関する説明も行う必要があります。マイナス面を避けた営業トークは顧客に不信感を与える要因になるので、営業担当にとって不利な話だとしても隠さず伝えるようにしましょう。
ただし、マイナスの要素を伝える際は必ずフォローアップを実施することを忘れないようにしましょう。例えばコストは高いが品質が良いといった風に、問題点を伝えるだけで終わらないことが重要です。
伝えたいことを端的に
営業トークを準備する際は、話の要点が伝わりやすいように内容を最適化することが大切です。言いたいことを言っているだけでは主題が分かりづらく、顧客のニーズや悩みを引き出すことも見込めません。
説明や返答は短くまとめ、結論を先に伝えることを意識しましょう。営業担当が長々と話すのではなく、顧客の方から話しやすい流れを作ることが大事です。
商談に時間をかけても成果が上がらない場合、話し方や説明内容を一度見直して改善点を探してみましょう。よく見られる失敗例としては、相手の反応を見ずに準備したことを読み上げるばかりになっている、もしくは信頼を得ることに集中しすぎて雑談に時間を費やしている等があります。
今挙げた2点は当事者が問題を把握できていないケースが多いので、自分で原因がわからない場合はどちらかを疑ってみることをおすすめします。
また、顧客に合わせたベネフィットを提案するには多くの情報が必要です。表面的なインタビュー以外にも、潜在ニーズを引き出す問題提起や、情報を引き出せる環境作りなどを効率良く進めなければなりません。
営業トークの内容に一貫性を持たせて話を引き出しやすくし、専門用語を一般表現に言い換えて分かりやすくするといった工夫も必要になってきます。
お客様の市場を把握しておく
営業活動を効率良く進めるには、相手の主力事業や取引先、競合他社といったデータを分析して市場動向を把握しておく必要があります。事前に営業を行う業界について知識を得ておくことで、相手に合わせた営業トークを行うことができます。
市場調査を実施する際は、具体的な目的を決めておくと手際よく調査を進められます。例えば「市場で売れている商品を把握して自社製品との違いを見極める」といったように、問題解決に役立つ情報を得られるように目的を決めると効果的です。
リサーチ手段としてはアンケート調査やインターネット上の資料閲覧などが一般的です。収集したデータを自社で分析、各部門へ共有することで今後の営業効率を高めることができます。
市場調査で得た情報が正確であるほど、顧客に合わせたベネフィットを予測しやすくなります。さらに、分析結果を商品開発にフィードバックすることで品質向上にも繋がります。
手早く具体的な情報を得たい場合、顧客の同業他社に対して営業を実施すると、市場動向や企業間の関係を効率良く把握することができます。獲得した情報を顧客へ伝えることで、表面的な話題よりも効果的にニーズを引き出しやすくなります。
ベネフィットの作り方とは?

ベネフィットはどのように作るのでしょうか。ここからは、ベネフィットの作り方の中でも、代表的なFABの法則についてご紹介致します。
FABの法則
FABとは、Feature(機能・特徴)、Advantage(効果)、Benefit(ベネフィット)の頭文字を取ったものです。ダイレクトレスポンスマーケティングの世界で有名な、マイケル・フォーティンがブログで提唱した公式です。
FABの法則では、
- 売りたい商品やサービスの機能・特徴を把握
- ○○の機能があるからこそ△△の利点がある、という効果を得る
- その生まれた効果によって作られる将来の利益がベネフィットとなる
お客様は特定のサービスや商品の機能が欲しいわけではなく、あくまでもそこから得られる結果であるということを念頭に置きましょう。
例えば、大学生がB5サイズの大学ノートを欲しいとすると、B5サイズのノートならほとんどの鞄に入ります。つまりコーディネートで鞄を変えたいときにも鞄選びに困ることはない、となります。
鞄選びに困ることがない(ベネフィット)からB5サイズのノートなのであって、ノートの中身が50行である(機能)から選んでいるわけではありません。
Feature(機能・特徴)を挙げる
FABの法則におけるFeature(機能・特徴)とは、特定のサービス、商品が持つ「スペック、特徴、機能」とは何かというものです。事実であり客観的な部分です。
例えば、ドラム式洗濯乾燥器であれば、下記のような内容です。
- 性能、容量:11.5Kg
- 標準使用水量:92.5L
- 商品重量:85.5kg
- 梱包サイズ:110.6×80×60cm
- カラー:灰色
- 右開き奥行スリムタイプ
このような機能、特徴は、購入に向けて他社製品との比較検討段階に入っている人には、判断材料として必要なポイントです。特にベネフィットに繋がるような、Feature(機能・特徴)を説明することが重要です。
サービスや商品の特徴を把握していないとベネフィットは作れないので、不明確な機能や把握できていない特徴がないかよく確認しておきましょう。
Feature(機能・特徴)によるAdvantage(効果)を挙げる
Feature(機能・特徴)を洗い出したら、次はAdvantage(効果)を挙げていきます。
ドラム式洗濯乾燥機であれば、
- 12L大容量であるため、家族全員の衣類を一度に洗濯が可能である
- 乾燥機付きなので、洗濯物を干す必要がない
- ドラム式の形状であるため、洗濯物の取り出しが楽でいい
というもので、その機能によってどんな効果が生まれるのかという多くの人に働くメリットの部分です。
すぐに思いつかない方は、Feature(機能・特徴)を洗い出したら、それに対して「~なので」という言葉を後ろにくっつけて、それに繋がる文章を考えましょう。
上の例なら、「乾燥機付きなので干す必要がない」といったものです。
Advantage(効果)を顧客視点に変換する
Advantage(効果)を顧客視点に変換したもの、それがBenefit(ベネフィット)です。
あるいは、Feature(機能)が顧客にとって何を意味するのかを考察する切り口でもBenefit(ベネフィット)を理解できます。
今度はAdvantage(効果)に対して、「~、つまり~」という言葉を後ろにくっつけましょう。それに繋がる文章を考えれば、それがBenefit(ベネフィット)になります。
例えば、「大容量の洗濯機なので一度に沢山洗濯ができる。つまり、洗濯時間を大幅に削減できることで、時間を趣味に充てたりお昼寝をしたりできる」となります。
そう提案をすれば、毎日忙しい中で家事をしなければならない人には刺さるでしょう。
また、極端な例ですが、「洗濯のストレスがなくなることで、仕事の生産性や集中力が上がる。つまり収入が上がった、という声があります」と提案をすれば、ビジネスマンにとって興味を持つ洗濯機になる可能性があります。
その商品を取り入れることで、どんな風に未来がプラスに変化するのか、という将来の利益がイメージできれば欲しいと思ってくれるでしょう。
営業時にベネフィットを感じてもらうために

営業効率を高めるには、商談の過程で顧客自身がベネフィットを理解し、納得できるように話を組み立てる必要があります。もちろん簡単な話ではありませんが、基本的な心がけや話の運び方を理解、実践していくことが営業の精度と効率を高める第一歩となります。
状況のヒアリング
どのような商品だとしても、相手にとって需要が無ければ商談に応じてくれる可能性は非常に低いと言えます。自社の商品やサービスに対する需要を的確に把握するには、ヒアリングを実施して相手が抱えている問題や、実現したい要望を聞き出すことが必要になります。
顧客に対応したベネフィットを伝えるには、まず顧客が抱えている問題やニーズを把握しなければなりません。ヒアリングで得た情報から顧客の課題や潜在ニーズを予測して、直接質問する過程を繰り返すことで効率的に営業を進めることができます。
顧客の発言を質問形式で再確認することによって、顧客自身が無意識に持っていた悩みや要望を自覚しやすくなります。そして、営業担当が実感を込めて同意、共感を示すと一層効果的です。
また、必要な情報を聞いたら出来るだけ話を展開させることがポイントです。ヒアリングは相手にベネフィットを提案する前準備であり、話を聞いただけでは意味がないので注意しましょう。
徐々に信頼関係を築く
営業トークの質が良くても中々契約を取れない場合、営業担当が顧客から充分な信用を得られていないことが考えられます。
商談の準備は入念に行っていても、最初の挨拶や自己紹介を雑にしてしまう営業担当は意外に多いとされます。話を始める前に相手の信用を損ねてしまうと、後からフォローすることは難しいでしょう。しかし、最初に話しやすい状況を整えられると営業効率がアップするため、自己紹介は確実に実施するようにしましょう。
また、目立った成果を上げようとして強引な営業トークを展開することも避ける必要があります。1度の商談で顧客から信用を勝ち取ろうとすると、却って信用を失う結果を招きます。例えば、専門用語を説明なしに多用し、相手の返答を遮って営業担当者が話すことは避けるべきでしょう。
商談でミスを重ねすぎると、営業担当者だけではなく会社全体のイメージを悪化させてしまいます。説明や回答を行う際には、顧客の調子に合わせて進めていくように心がけると信頼を得やすくなります。
提案サービスの必要性を伝える
ヒアリングによって顧客が持つ要望や課題を把握できたら、自社の製品やサービスが持つベネフィットを提案することで購買意欲を引き出していきましょう。
顧客にとって一定のニーズがある物でも、決裁者に話を通すのが難しそう、導入を検討する暇がない等で後回しにされるケースは珍しくありません。優先的に検討してもらうには、商談を先延ばしにするリスクを伝える必要があります。
ベネフィットを意識した営業に慣れていない場合、商品やサービスを導入することで得られる結果を紹介するようにしておくと、顧客のニーズに合わせた営業トークを行いやすくなります。
ベネフィットに関する情報を共有出来たら、自社のサービスや製品によって相手の悩みやニーズを解決できる根拠や方法をアピールしていく段階に移ります。自社を選んでもらう決め手を与える過程であり、具体的な解決策を提示することで顧客の不安要素を取り除くことが重要になります。
ヒアリングやベネフィットの提供などが上手く進んでいれば、顧客にとって足りないものを顧客自身が認識できていると思われます。そこで企業側から要求案件を再確認することで、顧客が自発的に決断できる状況を整えていくことができます。
最終的な決断に関しては無理に同意を引き出そうとせず、営業している商品やサービスを「必要だ」と思わせるように話を進めていくことが重要です。
ベネフィットを中心に伝えるメリット
ベネフィットを中心に伝えるメリットとしては、顧客が自分ごととして捉えやすくなる、顧客の感情を揺さぶり購買意欲を掻き立てられる、などがあります。
次の段落で詳しくご説明します。
顧客が自分ごととして捉えやすくなる
たとえ特定の商品の特徴や機能が良いと説明を受けたとしても、満足できないお客様が多いのが現状です。特徴や機能の説明はベネフィットではありません。
お客様は将来の利益(ベネフィット)を中心に示されれば、自分の将来を具体的にイメージでき、自分ごととして捉えてくれるようになります。
これにより、そのお客様は顧客になってくれる可能性が高くなります。
その際、営業に求められるのは、「この商品やサービスのベネフィットとはこれだ」と決めつけることではなく、顧客次第の状況を察し、その顧客にとってのベネフィットを提示することです。
顧客が知りたいことは商品の特徴ではなく、その商品を得ることで悩みを解決できるかどうか、解決した後はどうなりたいか、などの恩恵であり、自分が将来どうなっていたいかが重要なのです。
感情を揺さぶり、購買意欲が湧く
将来の利益(ベネフィット)を中心に伝えることで、顧客の感情はプラスに働くでしょう。感情がプラス要因に働けば、その商品の持つスペック以上の魅力が感じられるかもしれません。
購買意欲を掻き立てられている状態であれば、たとえ他の商品とのスペックや価格の比較をされたとしても、サービスや商品を購買してくれる可能性が高くなります。
顧客にとって商品を買うとは、理想的な解決策や魅力的な結果にお金を払うという意味であり、商品やサービスを得ること自体ではないことを、売り手は把握する必要があります。
顧客にベネフィットトークをする際には、その顧客がサービス、商品を使ってどうしたいのか、何を解決したいのかを正確に理解して話すと良いでしょう。そうすることで、顧客の感情や購買意欲は、売り手にとって良い方向へと向かいます。
まとめ
ベネフィット型営業を心がけていると、顧客が発言したことから悩みやニーズを予測して話を展開する場面が多く出てきます。営業担当者が一歩先回りして潜在ニーズを提起することは大切ですが、先回りしすぎると顧客に内容が伝わらない可能性が高いので注意が必要です。
ベネフィットを提案する目的は、顧客が納得したうえで契約してもらうことであり、営業担当が知識を披露することではありません。ベネフィット型営業の必要性や流れを正しく理解して実践することが、営業効率を上げる第一歩となります。
この記事を読んだ方におすすめ
・営業に役立つビジネスフレームワーク10選
・求められる5つの営業能力とは?営業力向上を目指すために
・営業成績は”雑談”で決まる!関係値が高まる営業トークのコツとは?