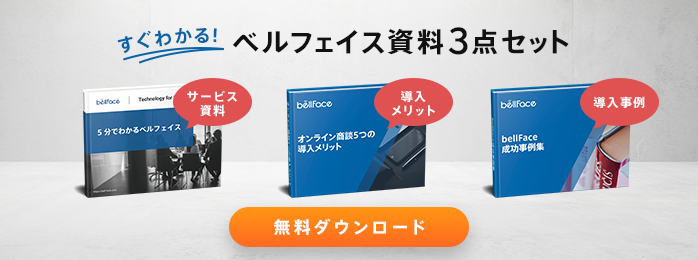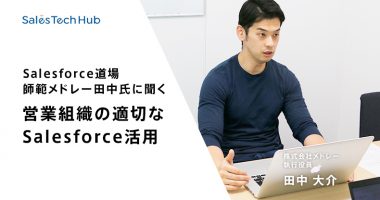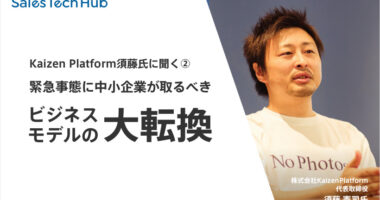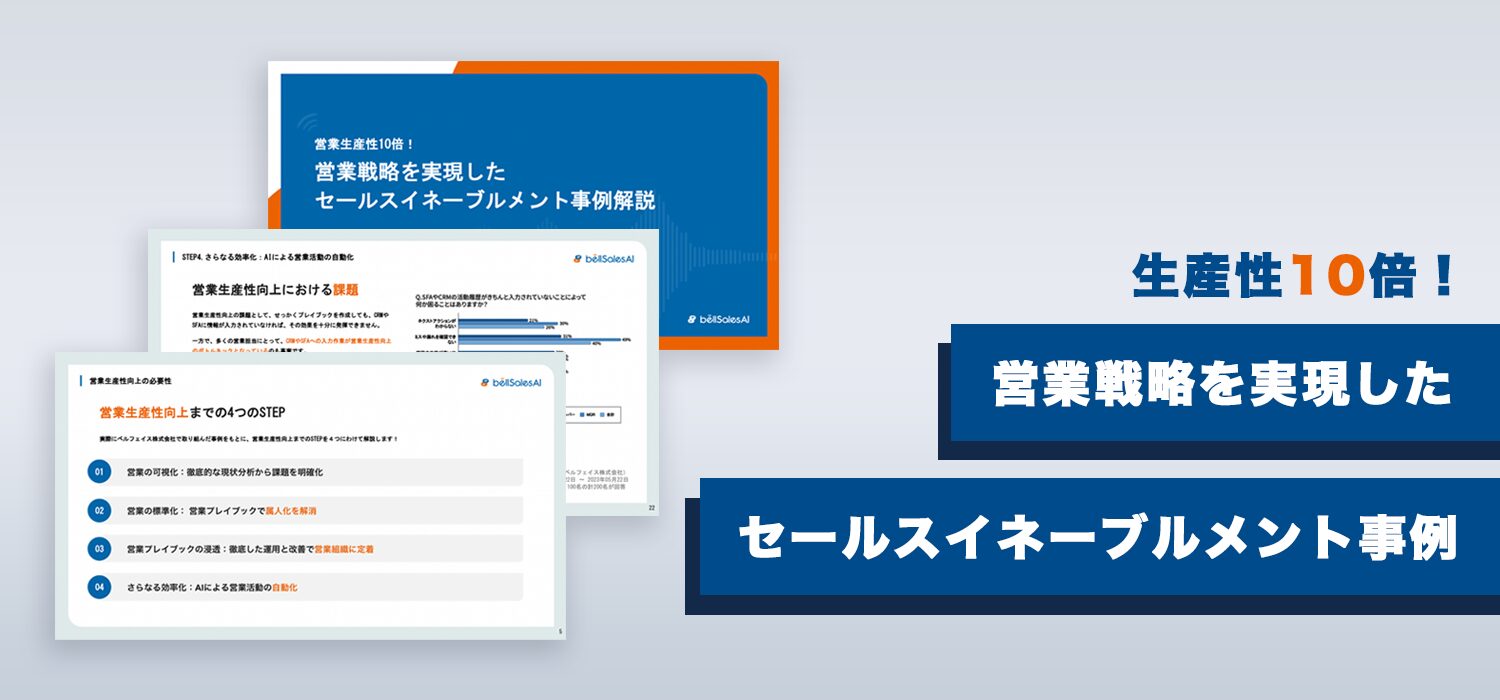売上の向上。それは企業の営業組織に所属している全ての人が叶えたい目標です。営業という仕事は、成果が上手く出ていれば非常にやりがいがありエキサイティングに感じる職種である一方、成果が出ていないときは本当に辛い職種でもあります。
今回は、2020年1月に株式会社マツリカのセールスマネージャーに就任し、たった3ヶ月でチームの1人あたりの売上金額をなんと6倍にした中谷さんにインタビューをしました。
1月からセールスMgr.やって、自社の営業コンサル的な動きをし改革してみて、、
1〜3月四半期で、前四半期と比較すると、『一人当たり売上(契約)金額』が5.96倍になりました。
そして4月からは、チームの人数が2倍になりました。
引き続き精進します。
— Nakatani/SalesTech in LA🇺🇸🇯🇵 (@midvalley2nd) April 1, 2020
中谷さんは「セールスというアートをサイエンスし、日本の営業をアップデートする」というモットーを抱え、様々な情報発信もされています。そのモットーや活動なども絡めながら、今回これだけ圧倒的な成果を出された経緯をお伺いしていきたいと思います。この記事は
- 営業組織のマネジメントをおこなっているマネージャー・リーダー
- 成果を出せずに伸び悩んでいる営業職
におすすめの記事です。
(本記事はオンラインで取材しております)

株式会社マツリカ Managing Director / Sales Science Lab,Inc.
CEO 中谷 真史さん(Twitterはこちら)
新卒にて外資系製薬企業MRとしてトップセールスを経験後、ベイカレント・コンサルティング、リブ・コンサルティングを経て独立、Sales Science Lab, Inc. を創業。同時に㈱マツリカにてSFA/CRMの事業に従事。モットーは『セールスというアートをサイエンスし、日本の営業をアップデートする』。
自社ツールSensesを使った自社の営業改革という面白いお題
ーQ. まず最初に、マツリカさんの事業内容や中谷さんの業務内容を教えてください。
中谷さん(以下敬称略):弊社株式会社マツリカは、SensesというSFA/CRMサービスを提供しています。いわゆる営業支援ツールでして、日々の営業活動の情報や取引先の情報などをSensesで毎日管理することで、売上を向上させるための示唆を提供するようなツールです。
ーQ. SFA/CRMのサービス、今たくさんあると思うのですが、Sensesの特長はどういったところにありますか?
中谷:今日本には約50~60社くらいのサービスがあります。うちはその中でも最後発の部類でして、最も新しいSFA/CRMと言えるかと思います。
この領域は1999年にアメリカはサンフランシスコでSalesforce.com社が設立されたことに端を発するのですが、約20年間が経った今もなお、営業支援ツールで解決できていないペインがたくさんあります。
中谷:例えば、ツール自体を「難しくてなかなか使いこなせない」だったりとか、管理者目線のものになってしまっているので現場からすると「『やらされ感』や『管理されている感』が強く、使いたくない」だったりとか、結局組織に根付かず、導入した会社のうち過半数が失敗に終わるとも言われています。
中谷:Sensesは後発であるが故に、シンプルなUI/UXから現場の営業職が使いたくなるような設計にしているのが特長になっています。
ーQ. 中谷さんはマツリカで何をされているんでしょうか。
中谷:私は2018年10月にマツリカにジョインしまして、そこから2019年12月まではCSM部門の統括をしていました。その後、今年(2020年1月)からセールスチームのマネージャーに就任しました。
中谷:私は新卒1社目で営業を経験し、その後はコンサルティングファームで営業改革を中心に経験してきました。営業の改革にはSFA/CRMの領域も必ずスコープに入ってくるため、当時からこういったツール活用の重要性は認識していました。
コンサルタントの仕事はSaaS企業のカスタマーサクセスマネジメント職と非常に近しい部分もあるため、マツリカ入社から1年強はこの部門の立ち上げ~統括をしておりました。
ーQ. 確かに、SFAツールのCSってある種営業コンサルのような側面はありますよね。今回異動されたのは、CSで蓄積したSFAのノウハウを自社の営業にも活かしたいということがあったのでしょうか。
中谷:そうですね。自社ツールSensesを使った自社の営業改革をやってくれと面白いお題をもらいました。
営業コンサルである自分がマネージャーとしてどれくらい成果が出せるのかという話と、Sensesを使って本当に営業成績が上がるのかという話を実証するべく、セールスに異動しました。
セールスというアートをサイエンスし、日本の営業をアップデートする
ーQ. なるほど、そういう背景だったのですね。中谷さんは自身のモットーとして「セールスというアートをサイエンスし、日本の営業をアップデートする」というフレーズを掲げていますが、やはり自社の営業チームの改革も”科学的に”おこなっていくのでしょうか
中谷:元々私は外資系の世界最大手の製薬会社でMRをしていたのですが、営業成績でNo.1の成績をおさめていました。
一般的にそれなりにすごいことかなと思うのですが、ただ私って別にお話が得意とか、面白いとか、プレゼンがうまいとかそういうわけではないのです。
どちらかというとそういうセンスはない人間だと思っています。しかしそういう人間でも営業成績で1位を取れるんですね。
中谷:純粋に面白い方・話が上手な方が営業成績が高いのは、それってもうセンスですよねと片付けられてしまうのですが、私の場合そうではなく、再現性のある営業の型を持っているからだと考えています。
営業はもちろんクリエイティブな職種なのですが、7~8割くらいの土台はサイエンスできる部分なのではないでしょうか。
MRからコンサルファームに転職してからも理論を磨いて、多くのお客様の売れる仕組みづくりに貢献してきたので、その経験から営業を科学する取り組みを続けています。
失注分析からインパクトの大きい改善施策を打っていく
ーQ. では本題の売上金額を6倍にしたこの3ヶ月で何をされたか聞いても良いでしょうか。
中谷:はい。まずやったことは失注分析です。改めて、過去3年分の失注を見返して、失注要因を洗い出しました。
ーQ. まず3年分の失注理由がしっかり蓄積できているのがさすがSFA提供企業ですよね(笑)
中谷:まあこれはどんなSFAでもできることですが、やっぱり失注分析はSFA導入において最も価値が高いポイントの一つですよね。受注率が仮に20%だとすると、10回の商談のうち8回は失注するわけですから、ここを探ることが当たり前ですが重要です。
中谷:弊社の場合、この失注理由を洗い出していくと、機能要因と営業要因の大きく2つに分類できました。
機能要因は「お客様の欲しい機能がないから」という話なんですが、これはプロダクトへの機能要望につながったり、もしくはリードのターゲティング・獲得したリードから商談化へのスクリーニングへの改善に活用できます。
一方で営業要因という部分が主に商談・受注率への改善ポイントになってくるわけです。
ーQ. 貴社の場合どのような営業要因での失注が多かったのでしょうか。
中谷:弊社の場合大抵は法人内の決裁・意思決定ルートが不明瞭で失注するケースと、時期ズレしてしまうものでした。失注の半分以上はこれが要因でしたね。
ーQ. ではこの2つへの対策をまず行っていったということですかね?
中谷:はい。一般的な受注率が20%くらいだとすると、残り80%が失注している中で、その半分がこの2つの要因ということなのであれば、これを解決すれば受注率は理論上60%になるわけですよね。
まあこれは言いすぎかもしれませんが、失注したもののうち2割でも受注できるようになれば、受注率28%になって受注が1.4倍になるんですよ(失注80%のうち半分のさらに2割が8%)。だから失注理由の分析・分類とそれへの対策って非常に重要なんです。
中谷:というように、改善するインパクト・ROIまで、ある程度考えながらその施策を打ちますね。
ーQ. 確かに、インパクトの大きい施策から手をつけていかないと成果は出ませんよね。ではその失注理由に対してどのような施策を行ったのでしょうか。
中谷:行ったことは本当に色々ありまして、全部で17個です。こちらについては私のnoteでもまとめてますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思うのですが、特に前述の時期ずれや決裁・意思決定ルートの特定漏れに対して行ったことは、3つあります。
中谷:1つ目はSDR(Sales Development Representative:反響型のインサイドセールス組織)を中心とした案件見極めの精査です。時期ズレを起こしやすい案件の特徴を掴み、SDRの一次スクリーニングの基準を変更しました。
SDRによるアポ質の精査は非常に重要で、時期ズレの対策以外にも、無駄アポを防ぐ点での活用や受注単価を上げるための取り組みでもここのスクリーニングを強化しています。
インバウンド中心の弊社のセールスにおいてこのスクリーニングは、すなわちターゲティングと同義だと考えています。
中谷:2つ目は商談資料の改訂です。営業が使う資料は当時プロダクト紹介資料や自社紹介資料などなどかなりの数ありまして、これを統一しないことには初回商談の流れをチームとして握ることは不可能だと感じていました。
商談資料さえチームで統一してしまえば、マネージャーである私が同席しなくとも、ある程度商談の流れと質を担保することができるようになります。
中谷:そして3つ目は商談のフェーズ設計です。当時商談のフェーズ管理に少し曖昧な部分があった結果決裁・意思決定フローが曖昧になったり時期ズレを起こしてしまっていたため、「誰と何を合意したか」について細かくSFAに盛り込み、フェーズ管理をしていきました。
中谷:本当に色々実施したのですが、特に今回の成果に結びついたのは1つ目のSDRのスクリーニング強化だったかなと思います。そもそも、売上成績って「(商談数✕成約率÷リードタイム)✕平均単価」から成り立ちますが、短期でこの成果を上げなければならないときは平均単価を操作するのが1番即効性があると考えています。
- 商談数を増やしてもマネージャーが把握しきれず質をコントロールできない
- 受注率向上は地道に行っていくものなので時間がかかる
- リードタイム短縮は即効性ある施策もあるが、大きな成果は見込めない
と消去法的ではあるのですが、案件の単価を上げるのが最も成果へは近道だと思います。
ーQ. 最も成果につながったというSDRを中心とした案件のスクリーニングはどのようにおこなっているのでしょうか。
中谷:主には規模・難易度・検討時期・必要な機能などからスクリーニングをしています。例えば企業としての検討なのか個人としてなのかで単価は左右されますし、いつ検討するかでも変わってきます。
業界によってはSFAに対して必須の機能などもあり、そのあたりの機能開発がないとまず受注できない場合などもありますので、業界毎に架電のスクリプトを変え、そういった機能は事前にヒアリングするようにしています。
SDRのヒアリング事項を精査して、スクリーニングに必要な情報を事前に取るようにしました。また、その上で初回アポイント前にセールスも自ら再度架電をすることでアポイントの質を究極まで高め、商談の質は劇的に向上しました。
このようにして、SFAの活用によって『狙って』実績を作っていくことは可能になります。現在、Sensesユーザーにおいては中央値で一人当たり売上高が利用15ヶ月後に39.6%増加したというエビデンスは報告されていますが、この成果をより大きくしていくのが僕の目標でもあり会社の使命でもあると思っています。
まとめ
「営業を科学する」という言葉は、近年良く使われるようになってきましたが、実際に科学的に営業組織を改革し、確かな成果を残している企業はまだ少ないのではないでしょうか。
中谷さんはマネージャー就任からたった3ヶ月でチームの1人あたり売上金額6倍という確かな実績を、失注分析とその要因の対策から生み出しました。SFAを活用しきれていない皆様も、まずは過去の商談の失注分析から始めてみてはいかがでしょうか。
この記事を読んだ方におすすめ
・商習慣の激変で営業はどうなる?未来の処方箋
・リモート商談で成果が出せない営業必見!コロナ禍でも売るためのヒントが満載の「シン・セールス理論」はなぜ生まれたのか?
・2021年BtoBマーケティング大予想「大手企業のデジタルマーケティング投資が本格化する」